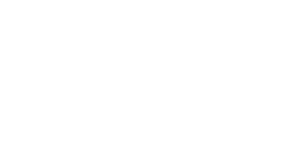皆さんは歌舞伎といえば何をイメージするでしょうか?
白塗りで鮮やかな隈取をした役者さんや、豪華絢爛な衣装などを連想する方は多いと思いますが、中には緑・オレンジ・黒の縦線のあの独特の柄が思い浮かぶ方もいらっしゃるはずです。
歌舞伎のことをあまりよく知らない方でも、株式会社天乃屋さんから発売されている大人気の美味しいお煎餅、歌舞伎揚のパッケージに描かれている模様であればご存知方も多いのではないでしょうか。
しかし、あの模様が、定式幕(じょうしきまく)という歌舞伎の舞台で使われる引幕で、長い歴史があり、様々な意味が込められているということまで把握している方は決して多くないとは思います。
このページでは、歌舞伎を象徴する重要な道具の一つ、定式幕を中心に、歌舞伎の幕についてご紹介していこうと思います。
目次
定式幕とは?

定式幕は歌舞伎の舞台で使用される引幕です。 引幕とは客席と舞台を区切るために、舞台の端から端いっぱいに引かれる幕のことで、芝居の幕開きと終幕(幕切れ)に用いられる重要な幕です。幕開きは、舞台に向かって左手の下手側から右手の上手側に向かって、終幕の場合は反対側の舞台に向かって右手の上手側から左手の下手側に人力によって引かれます。
名前の由来となっている「定式」とは「決まったやり方、定められた儀式」という意味で、歌舞伎や舞台の世界では良く使用される言葉です。 「いつも決まって使われる幕」という意味から、定式幕という呼称が定着していったといわれています。
定式幕の種類
定式幕には、配色が異なる3つの種類が存在します。
定式幕が使用されるようになった江戸時代は、芝居小屋で引幕を使用することは許されていませんでした。
しかし、江戸幕府が許可(官許)した「江戸三座」と呼ばれる芝居小屋、中村座・市村座・森田座は例外で、定式幕を使用することが許可されており、それは大変名誉なことだったということです。
ここからは、現在でも継承されている、江戸三座の定式幕の歴史や成り立ちについてご紹介したいと思います。
森田座式
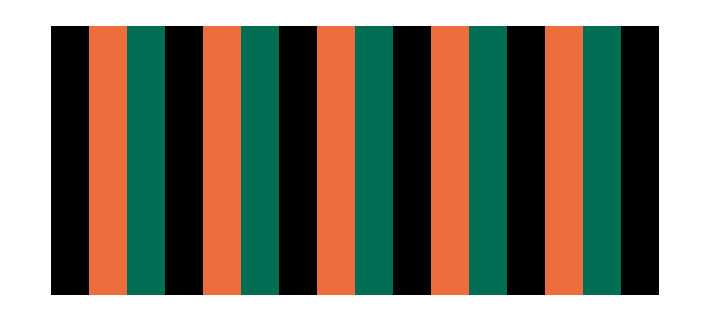
【配色】黒色、柿色、萌葱色(もえぎいろ)
【現在】歌舞伎座
現在、多くの人が歌舞伎を象徴する柄として認識しているのが、森田座(のちに守田座)発祥のこの【黒色・柿色・萌葱色】の順番で配色された、定式幕の柄なのではないでしょうか。
森田座は、1660年(万治3年)に森田太郎兵衛(初代森田勘彌)が木挽町五丁目(現在の中央区銀座6丁目)に開場したといわれています。その後、資金繰りに行き詰まり破綻・休座などを経て、1856年(安政3年)に十一代目森田勘彌によって森田座が再興。
その2年後には「森の下に田んぼ」では陽当たりが悪く実りが悪いので、これを「田を守る」に改めればきっと豊作になり、資金繰りも改善するに違いないという験を担いで、守田座に改称しました。尚、同じタイミングで森田勘彌自身も守田勘彌に改名しています。そして、1872年(明治5年)にはやはり「新たな富を求める」という験かつぎで、新富町(現在の中央区新富2丁目)へ移転し、3年後の1875年(明治8年)には座名も新富座と改めています。
尚、森田座式の定式幕が、現在は歌舞伎座で使用されている経緯は、明治初頭に名興行師として名をはせていた守田勘彌が、発足して間もない歌舞伎座に一時期招かれ、諸事万端を司っており、歌舞伎座が建つ木挽町はかつて森田座がその中心となって栄えた芝居町だったということから、自らの森田座式をちゃっかりと転用したのが切っ掛けで、今日まで定着しているといわれています。
中村座式

【配色】黒色、白色、柿色
【現在】平成中村座
そもそも定式幕の起源は、この中村座式の定式幕だと伝えられています。
1624年(寛永元年)当時、江戸における常設歌舞伎劇場の始まりといわれている、芝居小屋「猿若座(さるわかざ)」を建て座元として名声を獲ていたのが、初代中村勘三郎です。1633年(寛永9年)に初代中村勘三郎は、幕府の御用船「安宅丸(あたけまる)」回航の際に、船先で木遣り音頭を唄ったことで、巨船の艪の拍子を揃えた褒美として、将軍家より船覆いの幕(帆布)を拝領。その【黒・白・柿色】の順番で配色された幕を中村座で使用したのが定式幕のはじまりだといわれています。
現在では、森田座式の柄が定式幕の象徴として広く一般に知られているという印象を受けますが、実は中村座式の柄が定式幕の元祖だとされています。
ちなみに、2000年(平成12年)より公演を始めた平成中村座では、この【黒色・白色・柿色】の定式幕を踏襲しています。
市村座式

【配色】黒色、萌葱色(もえぎいろ)、柿色
【現在】国立劇場
市村座の定式幕の柄は、中村座式の柄をもとにして誕生したといわれています。当時、軒を連ねていた中村座の座元の娘が、市村座の座元のところへ嫁ぐことになった際に、その縁で市村座でも、中村座の幕を使うことができるようになったということです。しかし白は汚れが目立つので、のちに白色の部分を萌葱色に変えて使うようになったとされています。
市村座は、1634年(寛永11年)に村山又三郎が興した村山座が始まりで、後の1652年(承応元年)に市村羽左衛門が興行権を買い取ったことで市村座となりました。
当初は日本橋葺屋町(現在の日本橋人形町3丁目)にありましたが、火災と天保の改革の一環により、1842年(天保13年)に浅草猿若町(現在の台東区浅草6丁目)へ移転をします。
その後も、経営者の交代・関東大震災による焼失と復興など紆余曲折を乗り越えますが、1932年(昭和7年)に公演中の楽屋からの失火が原因で焼失した後は再建されず、市村座は 約300年の長い歴史に幕を閉じました。
しかし、1966年(昭和41年)に国立劇場(東京都千代田区)が開場すると、市村座式の定式幕が正式に採用されることになり、現在でも国立劇場を象徴する定式幕として活躍しています。
定式幕の色の意味

まず最初に結論から申し上げますが、定式幕の配色に関しては明確な意味や理由は分かっていません。
前述の中村座式の定式幕の項目で触れた通り、定式幕の歴史は、初代中村勘三郎が将軍家より拝領した、船覆いの幕を使用したことから始まったといわれており、そうなると配色には特に深い意味はないということになります。
しかし、一方では伝統文化とつながりのある「陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)」から定式幕の色が選ばれたのではないかという説もあるのです。
真相は藪の中ですが、陰陽五行説から色が選ばれたという説もとても興味深い内容なので、陰陽五行説のことをある程度把握したうえで、各々が想像を膨らませてみるのも面白いかもしれません。
陰陽五行説
陰陽五行説とは、中国の春秋戦国時代ごろに発生した「陰陽説」と「五行説」のそれぞれ無関係に生まれた考えが後に結合した思想のことで、別名で陰陽五行論ともいいます。を組み合わせたものである。
陰陽思想と五行思想が組み合わさったことによって、より複雑な事象の説明がなされるようになり、陰陽道などにおいては、占術などに用いられる事もあったといわれています。
◇陰陽説
陰陽説は、古代中国の思想に端を発し、森羅万象を様々な観点から陽と陰の2つのカテゴリに分類する思想や学説のことをさします。
陰陽説の一部具体例
- 太陽(陽)と月(陰)
- 光(陽)と闇(陰)
- 火(陽)と水(陰)
- 男(陽)と女(陰)
- 表(陽)と裏(陰)
- 上(陽)と下(陰)
- 夏(陽)と冬(陰)
- 肉体(陽)と精神(陰)
- 興奮(陽)と抑制(陰)
など
陰陽説は中国の戦国時代末期になると、五行思想と一体で扱われるようになり、次第に陰陽五行思想となっていったとされています。
◇五行説
五行説とは、5種類の元素から万物はなりたち、互いに影響を与え、支え合いながら変化と循環をしているるという思想で、木・火・土・金・水、色、方角、季節など、以下のように分類されます。
五行説:5つの要素
- 木【青、緑】
- 方角は東、季節は春、樹木が成長する様子を表す。
- 火【赤(紅)】
- 方角は南、季節は夏、炎のような情熱的な性質を表す。
- 土【黄】
- 方角は中央、季節は春夏秋冬の土用、万物を育み保護する豊かな性質を表す。
- 金【白】
- 方角は西、季節は秋、金属のような硬くて冷徹な性質を表す。
- 水【黒】
- 方角は北、季節は冬、生命の源泉であるという意味を表す。
このような五行説の5つの要素の中から、縁起を担ぐといった意味で、歌舞伎と相性が良さそうな3つをピックアップして定式幕を作ったのではないかともいわれています。
定式幕以外に歌舞伎で使用されれる幕
定式幕以外にも、歌舞伎では様々な幕が使用されます。使用目的も様々で、舞台と客席を遮断して開幕や閉幕を告げる以外にも舞台装置・演出に欠かせない重要なアイテムとして機能しています。ここからは歌舞伎で使われる代表的な幕をピックアップしてご紹介いたします。
緞帳(どんちょう)

緞帳は、劇場に掛けられている上下に開閉する幕のことをさします。客席から部隊全体を隠すためのとても大きな幕で、開演中以外は基本的に常に掛かっています。開場後開演までの間、及び終演後もお客さんの目に長時間触れるため、印象に残りやすく、その施設の顔といっても過言ではありません。そのため、現代の劇場の緞帳は綴れ織りなどの豪華絢爛なものが大半を占めています。
しかし、江戸時代から明治初期頃までは、簡素で粗末な巻き上げ式の幕のことを緞帳と呼び、引幕の使用を許されていない小芝居(小規模な劇場)を中心に使用されていました。
やがて、明治後期あたりからは、西洋式の劇場が建設され、西洋演劇の影響を受けて、緞帳は豪華絢爛なものという認識が広まりましたが、これは江戸時代の緞帳とは別物と考えた方がよいでしょう。
尚、歌舞伎を上演する大劇場には現在、豪華な緞帳が設置されていますが、古典歌舞伎の幕開きには基本的に定式幕が使用されています。緞帳で幕開きするのは、松羽目物(能の様式を取り入れた舞踊劇)や新歌舞伎(明治から昭和にかけて創られた文学的作品や舞踊)などごく僅かです。
霞幕(かすみまく)
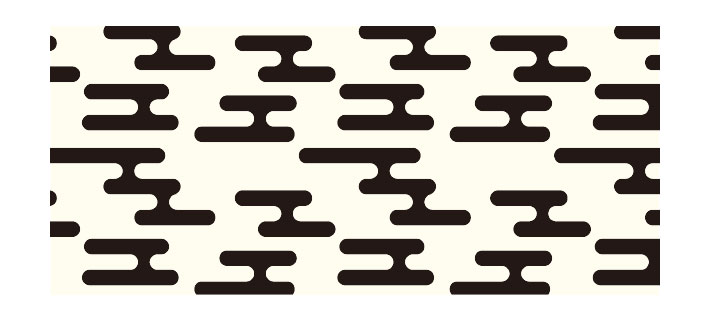
主に常磐津や清元などの浄瑠璃の演奏者が舞台に出入りする際や、演奏していないときに隠す転換の道具として用いられる霞幕。
白い横長の幕に、霞のたなびく模様が描かれているため、『南総里見八犬伝』の芳流閣の立廻りや、『白浪五人男』の大屋根の立廻りなどの、高所や遠方を望む場面で背景としても使用されています。
浅葱幕(あさぎまく)

空の色や空気・空間などを表現する、淡い水色で舞台全体を覆うように吊り下げられている幕のことを浅葱幕と呼びます。
浅葱幕は、基本的に日中の屋外の場面で使用されますが、立廻りの途中などで浅葱幕が上から一瞬で下りてきて舞台面を隠す「振りかぶせ」や、被せてある幕を一瞬で落とす「振り落とし」といった、歌舞伎ならではの転換技法にも使用され、視覚的に観客を楽しませることができる、なくてはならない道具です。
消し幕

消し幕は、芝居の進行上で不要になったもの(特に死んだ人物など)を舞台上から引っ込める際や、舞台上で俳優が化粧や扮装を変えるときなどに、目隠しとして使用されます。
消し幕には、歌舞伎において「見えていない」お約束になっている黒幕を使うのが基本です。ただ、歌舞伎十八番をはじめ、様式性の高い演目の場合は舞台全体の視覚的なバランスを考慮して、華やかな緋色(赤色)の毛氈、緋毛氈(ひもうせん)が使用される場合もあます。
道具幕

場面が移り変わる際に、そのつなぎとして使われ、背景大道具の役割を担う幕のことを道具幕と呼びます。
道具幕は、前後の場面が海ならば浪幕、山ならば山幕、屋敷などの場合は網代幕(あじろまく)というように、状況にあわせて使い分けがされます。
後ろ幕

夜や暗闇を表現する際には、舞台の背景をすっぽり隠すように掛けられる、後ろ幕と呼ばれる、主に黒色の幕が使用されます。
おわりに
歌舞伎は重要無形文化財として、国内外を問わず幅広い層から支持されている日本独自の伝統芸能です。
江戸時代から続く、この歌舞伎という素晴らしい文化をこれまで支え続け、そして未来へ継承していくためにも、幕は必要不可欠な道具としてこれからも変わらずに活躍していくはずです。