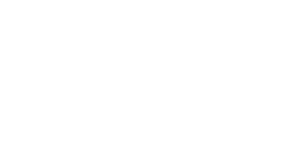お寺で行われる行事、あるいは伝統的なお祭りなどで、鮮やかな五色の幕が飾られているのを目にしたことはないでしょうか?
青(または緑)・黄・赤・白・黒(または紫)の帯状の布が連なったその幕は、見た目がただ美しいだけではなく、古くから日本に伝わる深い意味や願いが込められています。
五色それぞれの色の意味や由来、使用される場面など、このページでは五色幕の色々についてご紹介していこうと思います。
目次
五色幕の歴史

五色幕がいつ頃に誕生し、使われ始めたのかということに関しては諸説あり、その正確な起源を特定するのはとても困難ですが、五色幕で使用されている五色は、古代中国で成立した陰陽五行説に基づくものだといわれています。
日本では仏教が伝来した飛鳥時代以降、仏教儀礼・仏教美術の中で五色が重要な意味を持つようになり、徐々に認識されるようになったと考えられています。その後も、奈良時代には東大寺の大仏開眼供養など、国家的な仏教儀礼で五色が用いられていたといわれています。
時代を経た現代でも、五色幕は単なる装飾という域を超えて、仏教寺院・その他伝統的な儀式で不可欠な荘厳具として定着し、その形や意味合いは現代に受け継がれています。
五色幕に込められた想い

五色幕には、仏教の教えや世界の成り立ち、人々の願いといった様々な深い意味が込められています。
特別な日に五色幕を掲げることは、目に見えない尊い存在に対する敬意を表し、その場の清らかさや重要性を際立たせる行為であり、仏様や神様への感謝の気持ち、平和への祈り、五穀豊穣や幸福への願いなど、人々の様々な想いが込められているのです。
五色幕の色の意味と由来

五色幕で使用されている、五色それぞれの色には、仏教や日本の伝統的な考え方に基づいた深い意味が込められています。
これらの五色は、仏教においては五正色として、五智如来や五大明王など、様々な仏様や概念と結びついています。また、日本古来の陰陽五行思想とも関連が深く、木・火・土・金・水という五行が、それぞれ青(緑)・赤・黄・白・黒(紫)の色、そして方位や季節と結びついて世界の成り立ちを表すとも考えられています。このように、五色幕の色には、世界の構成要素や仏教の教え、人々の願いが象徴的に表現されているのです。
尚、五色それぞれの色が表している、具体的な意味については以下の詳細をご確認ください。
青(緑)色
仏陀(釈迦)の頭髪の色とされており、心乱れず穏やかな状態の禅定「定根(じょうこん)」を表します。
黄色
仏陀(釈迦)の身体の色。豊かな姿で確固とした揺るぎない性質「金剛(こんごう)」を表します。
赤色
仏陀(釈迦)の血液の色であり、人々を救済しようとする慈悲心が止やむことのない 「精進(しょうじん)」を表します。
白色
仏陀(釈迦)の歯の色とされ、清らかな心で様々な悪業や煩悩の苦しみを浄める「清浄(しょうじょう)」を表します。
黒(紫)色
仏陀(釈迦)の袈裟の色といわれており、あらゆる侮辱・迫害・怒り・誘惑などを抑えて耐え忍ぶ「忍辱(にんにく)」を表します。
五色幕が使用される場面

五色幕は、お寺などの仏教寺院、またはそれにまつわる建物を装飾するために使用されます。
また、神社などの神道関連の行事でも五色幕と同様の五色で構成された、『五色旗・五色幡(ごしきばた)』とよばれるのぼり旗のような道具で、神社の境内などを装飾します。
具体的には、仏教関連と神道関連の下記のような行事・場面で『五色幕』と『五色旗(五色幡)』はそれぞれ使用されています。
仏教関連の行事
お寺の新しい建物が完成した際の落慶法要や、仏像に魂を入れる開眼法要などの寺院における特別な行事、また、彼岸会や灌仏会(花まつり)、お盆などの年中行事、仏前結婚式などが執り行われる際に、お寺の本殿の大間・正面に取付けられます。五色幕は、本堂を荘厳するとともに、お釈迦様への敬意も表しています。
神道関連の行事
神社のお祭りや、神前結婚式、地鎮祭などの儀式では、『五色旗・五色幡(ごしきばた)』とよばれる、幕というよりは、のぼり旗に近い道具が使用されます。この五色の幡は、陰陽五行(おんようごぎょう)の思想に基くもので、懸けると願い事が叶うとされています。
『五色旗・五色幡』には、揺るぎない大地と順調な四季の移ろいの中で、自然の一部として生かされている自分を自覚し、無理のない生き方をすることが幸せの原点であるという、五行の順調な循環などの様々な意味が込められているといわれています。
おわりに
これまでは、お寺や伝統行事などで何気なく目にしていた五色幕も、色の意味や、込められた思いを深く知ることで、今までよりも身近なアイテムに感じられるはずです。
五色幕を深く知ることで、より興味を持って日本の文化や信仰の一端に触れる方が一人でも増えてくれればと思います。